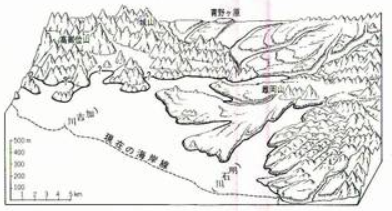
12.平岡町二俣探訪:印南野台地②・二俣は海の底
二俣を流れる新井用水は、10㍍の等高線に沿っています。
*江戸時代に造られた新井用水については、後日取り上げます。
だいたい新井用水から北、野口から東は明石川まで、そして美嚢川から南の範囲を印南野台地といっています。
昨日のブログで印南野台地を確かめておいてください。
「印南野台地もかつて海の底であった」と言われて、信じることができますか。
答えは、海の底だったのです。
それでは、印南野台地は、どのように形成されたのでしょうか。
図を見てください。この図は24・5万年前ごろの海岸線・水際線(推定)です。(図は『加古川市史(第一巻)』より)
現在の印南野台地は海の底です。もちろん、新井用水から現在の海岸線までは当然海の底になります。
この海に川を中心として周辺から土砂が流れ込みました。
土砂は、海底では比較的平に堆積します。
今度は、印南野台地にあたる海底の部分の隆起がはじまりました。
そして、比較的平らな海底であった海底が徐々に地上に姿を現しました。これが印南野台地です。
印南の台地の隆起のようすは一様ではではなく、東の隆起が大きく西の平岡・野口辺りでは規模の小さな隆起でした。
現在でも印南野台地の隆起は続いています。
隆起の速度は、二俣辺りでは年間0.125mmで、東の明石市魚住町辺りでは0.35mmとなっています。
印南野台地の誕生には、隆起作用の外に気候変動という、もう一つの要素が加わり特徴ある台地を作りあげています。
気候変動と印南野台地については、明日のブログで調べることにしましょう。
